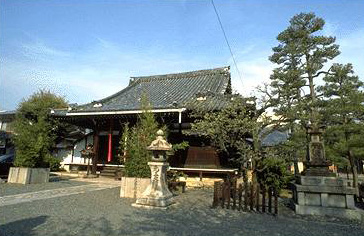見学スポットの検索結果
絞り込み検索
(エリア・カテゴリの条件を指定して検索結果を絞り込むことができます)
-
いけばなしりょうかんいけばな資料館
華道の歴史を学ぶならここです。いけばな発祥の地、六角堂・頂法寺(ろっかくどう・ちょうほうじ)に建つビルにあります。いけばなは飛鳥時代に仏前に花を供えることから始まり、室町時代に武家社会に根付き、江戸中期に庶民の家でも花を生けるようになり、全国に広がりました。ここでは華道家元池坊(いけのぼう)に伝わる花伝書などの古文献や花器、びょうぶ、掛け物など500有余年にわたる華道の史料が展示されています
更新日:2016年6月30日
- カテゴリ
-
- 洛中
- 美術館・博物館
華道の歴史を学ぶならここです。いけばな発祥の地、六角堂・頂法寺(ろっかくどう・ちょうほうじ)に建つビルにあります。いけばな …[続きを読む]
更新日 : 2016年6月30日
-
らいさんようしょさいさんしすいめいしょ頼山陽書斎山紫水明處
鴨川のたもとに生垣に囲まれたかやぶきの民家が見えます。江戸時代後期に学者や詩人として活躍した頼山陽が、晩年この地に住まいを構え、敷地内に建てた書斎です。ここから見える東山の山並みの美しさと、前を流れる鴨川の清らかさを「山紫水明」と言い表して書斎の名にしました。山陽は、文人などと幅広い交友関係を持ち、サロンのような場所となりました。有名な歴史書の「日本外史(にほんがいし)」はこの書斎で執筆されました。
更新日:2016年6月29日
- カテゴリ
-
- 洛中
- 名所・旧跡
鴨川のたもとに生垣に囲まれたかやぶきの民家が見えます。江戸時代後期に学者や詩人として活躍した頼山陽が、晩年この地に住まいを …[続きを読む]
更新日 : 2016年6月29日
-
きょうとしれきししりょうかん京都市歴史資料館
京都の歴史に関する資料が集められています。まず1階に入ると、コンパクトな展覧会が開催されているので、面白い京都の歴史と出合えるかもしれません。2階の閲覧室には、史料や図書が所蔵されており、写真や絵図なども閲覧できます。京都の歴史に関する簡単な相談も行っていますので、遠慮なくたずねてください。真ん前は自然いっぱいの京都御苑です。
更新日:2016年6月29日
-
にしじんおりかいかん西陣織会館
京の伝統産業「西陣織」が、どのように造られていくのか、パネルやビデオで生産工程が詳しく説明されています。人気を集めているのが、1階ホールで行われる「きものショー」です。西陣ならではの金糸や銀糸をちりばめた華麗な美しさで魅了されます。手機(てばた)の体験ができ、織幅20センチ、長さ30センチのテーブルセンター状のものが織れます。着物やネクタイのほか小物類の展示即売もしています。
更新日:2016年6月29日
- 〒602-8216 京都市上京区西堀川通元誓願寺上ル竪門前町414番地
-
市バス「堀川今出川」下車徒歩すぐ
- TEL: 075-451-9231
- FAX: 075-432-6156
- URL: http://www.nishijin.or.jp/kaikan/
-
【営業時間】9時〜17時
【休業日】12/29〜1/3
-
ろざんじ廬山寺
平安時代、紫式部(むらさきしきぶ)がこの地に住み、「源氏物語」を書き上げたといわれます。境内には白い砂と緑のコケが鮮やかな「源氏の庭」があり、庭園には「紫式部邸宅址」の石碑があります。お寺を開いたのは延暦寺(えんりゃくじ)の僧・元三大師(がんざんだいし)。大師の鬼退治にちなんで節分に行われる「鬼法楽」は、紅白の豆と福もちなどの威力に追われて、鬼が逃げ去り、悪霊退散(あくりょうたいさん)をお祈りするユニークな行事です。
更新日:2016年6月10日
- 〒602-0852 京都市上京区寺町通広小路上ル1丁目北之辺町397
-
市バス「府立医大病院前」下車徒歩3分
- TEL: 075-231-0355
- FAX: 075-231-1357
- URL: http://www7a.biglobe.ne.jp/~rozanji/
- E-MAIL: rozanji@ktf.biglobe.ne.jp
-
【時間】9時〜16時
※無休
源氏庭の拝観休み:1月1日・2月1日〜2月9日・12月31日
- カテゴリ
-
- 洛中
- 寺院・神社
平安時代、紫式部(むらさきしきぶ)がこの地に住み、「源氏物語」を書き上げたといわれます。境内には白い砂と緑のコケが鮮やかな …[続きを読む]
更新日 : 2016年6月10日
-
せいめいじんじゃ晴明神社
平安時代のすぐれた陰陽師(おんみょうじ)・安倍晴明(あべのせいめい)をまつっています。陰陽師とは、物事の良し悪しを占い、天皇や大臣に伝える人のこと。今でいえばカリスマ占い師です。この場所にはかつて安倍晴明の屋敷があり、晴明の活躍をたたえて、一条天皇がその跡地に神社を建てたといわれています。境内には飲むと病気が治るという「晴明井」などがあり、晴明の不思議な力に願いを託す人たちでにぎわっています。
更新日:2016年6月10日
- 〒602-8222 京都市上京区堀川通一条上る晴明町
-
市バス「一条戻橋・晴明神社前」下車徒歩2分
- TEL: 075-441-6460
- FAX: 075-415-0050
- URL: http://www.seimeijinja.jp/
-
【時間】9時〜18時
※無休
- カテゴリ
-
- 洛中
- 寺院・神社
平安時代のすぐれた陰陽師(おんみょうじ)・安倍晴明(あべのせいめい)をまつっています。陰陽師とは、物事の良し悪しを占い、天 …[続きを読む]
更新日 : 2016年6月10日
-
ちょうほうじ(ろっかくどう)頂法寺(六角堂)
本堂が六角形をしていることから「六角堂」と呼ばれています。聖徳太子が創建したと伝わるとても歴史のあるお寺で、室町時代ごろからは町民たちの集会所としての役割も持ち始めました。頂法寺の立つ位置は京都のちょうど真ん中にあたるとされ、それを示す「へそ石」が境内に残っています。いけばな発祥の地としても知られ、隣接して華道家元(かどういえもと)・池坊(いけのぼう)があります。
更新日:2016年6月10日
- カテゴリ
-
- 洛中
- 寺院・神社
本堂が六角形をしていることから「六角堂」と呼ばれています。聖徳太子が創建したと伝わるとても歴史のあるお寺で、室町時代ごろか …[続きを読む]
更新日 : 2016年6月10日
-
ぎょうがんじ(こうどう)行願寺(革堂)
寺を開いた行円(ぎょうえん)は、以前は猟師で、あるとき山中で鹿を射とめたところ、腹から小鹿が出てきました。後悔した行円は僧になり、その皮を衣にして念仏を唱えて修行したそうです。その姿から皮聖(かわのひじり)と呼ばれ、寺の名になりました。京都の町衆(まちしゅう)の集会所だった町堂(ちょうどう・まちどう)の役割と、西国三十三所札所としての信仰を集めてきました。行円が着たという鹿皮が寺に伝えられています。
更新日:2016年6月10日
- カテゴリ
-
- 洛中
- 寺院・神社
寺を開いた行円(ぎょうえん)は、以前は猟師で、あるとき山中で鹿を射とめたところ、腹から小鹿が出てきました。後悔した行円は僧 …[続きを読む]
更新日 : 2016年6月10日
-
ほんのうじ本能寺
明智光秀(あけちみつひで)が天下統一目前の織田信長(おだのぶなが)を攻め、自害させた「本能寺の変」で知られています。当時実際に本能寺があったのは現在の場所よりもっと西、四条西洞院あたりでした。光秀の襲撃で焼け落ちたお寺は、再建の途中、1592年に豊臣秀吉により転地命令を受け、現在地に移転。翌年に再建が完了しました。境内には織田信長一族や森蘭丸(もりらんまる)などの供養塔が残り、毎年6月第1土・日は信長をしのぶお祭りも行われています。
更新日:2016年6月10日
- カテゴリ
-
- 洛中
- 寺院・神社
- 車椅子で周れる施設
明智光秀(あけちみつひで)が天下統一目前の織田信長(おだのぶなが)を攻め、自害させた「本能寺の変」で知られています。当時実 …[続きを読む]
更新日 : 2016年6月10日
-
しょうこくじ相国寺
花の御所(はなのごしょ)と呼ばれた室町幕府3代将軍足利義満(あしかがよしみつ)の邸宅の東に造営されました。高さが109メートルもあった七重の塔は落雷で焼失、建物も応仁の乱で焼けてしまいます。のちに豊臣秀頼や徳川家康らの寄進で再建されました。法堂(はっとう)の天井に描かれた狩野光信(かのうみつのぶ)筆の大きな龍は、音に共鳴する「鳴き龍」として有名です。伊藤若冲(じゃくちゅう)や長谷川等伯(とうはく)などの絵画を展示している境内の承天閣美術館は必見ものです。
更新日:2016年6月10日
- カテゴリ
-
- 洛中
- 寺院・神社
- 車椅子で周れる施設
花の御所(はなのごしょ)と呼ばれた室町幕府3代将軍足利義満(あしかがよしみつ)の邸宅の東に造営されました。高さが109メー …[続きを読む]
更新日 : 2016年6月10日