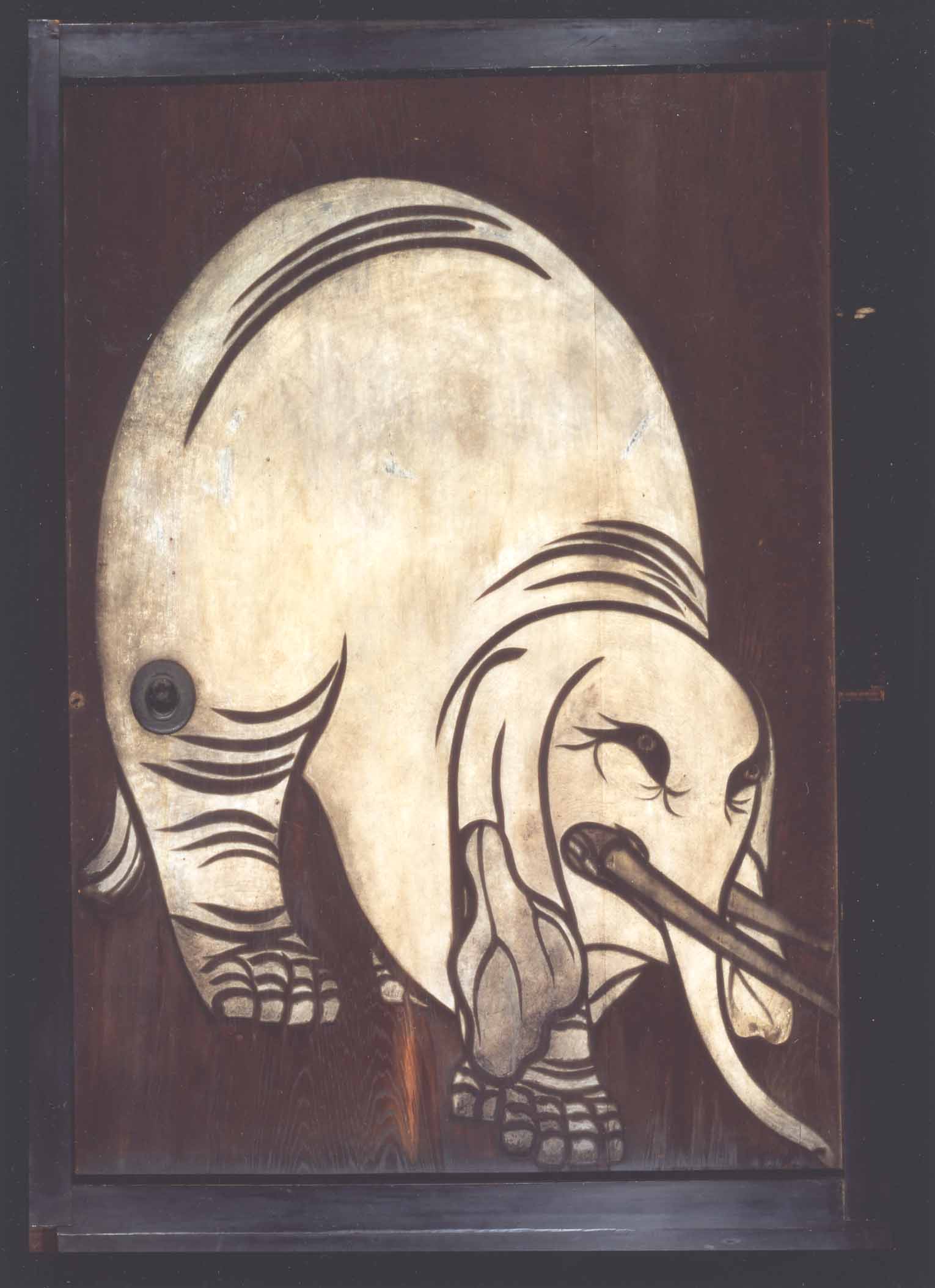見学スポットの検索結果
絞り込み検索
(エリア・カテゴリの条件を指定して検索結果を絞り込むことができます)
-
ろくはらみつじ六波羅蜜寺
空也が鴨川の東に寺を開き、弟子が現在の名前にしました。空也は諸国を歩いて社会事業を行い、身分の上下を問わない「口称(こうしょう)念仏」という布教で町中をまわり、「市の聖(ひじり)」と呼ばれました。その後この一帯は、平安時代末に平家一門の屋敷が立ち並び、鎌倉時代には六波羅探題を置きました。令和館には口から仏が飛び出している有名な空也上人像や平清盛像(ともに重文)が安置されています。12月に行われる「空也踊躍(ゆやく)念仏」が有名です。
更新日:2024年4月2日
- カテゴリ
-
- 洛東
- 寺院・神社
空也が鴨川の東に寺を開き、弟子が現在の名前にしました。空也は諸国を歩いて社会事業を行い、身分の上下を問わない「口称(こうし …[続きを読む]
更新日 : 2024年4月2日
-
ぎおんこうぶかぶれんじょうしょうげきじょう ぎおんこーなー祇󠄀園甲部歌舞練場小劇場 ギオンコーナー
京舞はじめ、狂言、舞楽、茶道、華道、筝など、7つの日本の伝統芸能・伝統文化を約1時間で身近に鑑賞できる施設。
更新日:2023年8月22日
- 〒605-0074 京都市東山区祇󠄀園町南側570-2
-
- JR「京都」駅より市バス206号「祇󠄀園」下車徒歩5分
- 京阪電車「祇󠄀園四条」駅より徒歩5分
- 阪急電車「京都河原町」駅より徒歩10分
- TEL: 075-561-1119
- FAX: 075-561-3860
- URL: http://www.kyoto-gioncorner.com/
-
【営業時間】毎日18時~、19時~
- カテゴリ
-
- 洛東
- アクティビティ・テーマパーク
京舞はじめ、狂言、舞楽、茶道、華道、筝など、7つの日本の伝統芸能・伝統文化を約1時間で身近に鑑賞できる施設。
更新日 : 2023年8月22日
-
きょうとこくりつはくぶつかん京都国立博物館
三十三間堂の向かいに建ち、1895年(明治25)に当時の有名な建築家・片山東熊(とうくま)が設計した特別展示館(国指定重要文化財)と、平常展示館があります。広々とした芝生の敷地に立つ石塔、噴水広場ではロダンの彫刻「考える人」が出迎えてくれます。主な収蔵品は、京都に伝来した考古品、社寺に伝わる仏像や宗教品、ふすま絵などのほか彫刻や陶磁器、染織など国宝、重文の貴重品多数を所蔵しています。日本を中心とした東洋の考古遺物と、古美術品の収集では、日本でも有数の博物館です。
更新日:2021年2月17日
-
きょうとでんとうさんぎょうみゅーじあむ京都伝統産業ミュージアム
長く都として栄えてきた京都では、茶道や華道、能をはじめとする伝統文化や人々の暮らしを支え、様々な伝統産業が発展してきました。「京都伝統産業ミュージアム」では、歴史の中で脈々と受け継がれてきた京都の伝統産業74品目とその背景を紹介しています。館内では、74品目の伝統産業を一堂に集めた展示に加え、それぞれの品目の詳しい解説のほか、製造工程の映像も見ることができ、完成品の鑑賞にとどまらず、その背景に興味がある方にもお楽しみいただけます。さらに、製品を作り上げるための多種多様な道具や素材の展示のほか、実物を見ながら製品として完成するまでのプロセスを感じることができる展示、おりんや京こまなどに実際に触って楽しめる展示も。伝統産業のものづくりの過程や技術・技法を肌で感じ、学び、楽しんでいただくこともできます。
更新日:2020年5月21日
- 〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1 京都市勧業館みやこめっせ地下1階
-
<市バス>
5系統、100系統 「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ
206系統 「東山二条・岡崎公園口」下車
46系統 「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車
<地下鉄>
地下鉄東西線「東山」駅1番出口より北へ徒歩約10分
- TEL: 075-762-2670
- FAX: 075-761-7121
- URL: https://kmtc.jp/
-
【営業時間】9時〜17時(入館は16時半まで)
【休日】年末年始、夏季休館日あり
- カテゴリ
-
- 洛東
- アクティビティ・テーマパーク
長く都として栄えてきた京都では、茶道や華道、能をはじめとする伝統文化や人々の暮らしを支え、様々な伝統産業が発展してきました …[続きを読む]
更新日 : 2020年5月21日
-
むりんあん無鄰菴
明治・大正の元老(げんろう=明治後期から昭和初期にかけて、天皇を補佐した政界の最高首脳)・山県有朋(やまがたありとも)が明治中期に京都に造った別荘です。庭園は山県自らが設計、有名な造園家・7代目小川治兵衛(じへい)によって作庭されました。疏水の水を巧みに取り入れ、東山の借景をいかした庭園は、ゆったりした気分にひたれます。昭和26年国の「名勝」に指定されました。洋館は、伊藤博文らによる日露戦争開戦直前の「無鄰菴会議」が開かれたことで知られます。
更新日:2019年4月1日
- カテゴリ
-
- 洛東
- 名所・旧跡
明治・大正の元老(げんろう=明治後期から昭和初期にかけて、天皇を補佐した政界の最高首脳)・山県有朋(やまがたありとも)が明 …[続きを読む]
更新日 : 2019年4月1日
-
しょうれんいん青蓮院
天台宗の門跡寺院で非常に格式が高く、粟田御所(あわたごしょ)と呼ばれました。天明の大火(てんめいのたいか)の時に天皇が避難したこともあります。このお寺で出家した親鸞聖人お手植えと伝わる樹齢800年の大きな楠(くすのき)は京都市の天然記念物に指定されています。宸殿(しんでん)、小御所(こごしょ)、本堂(ほんどう)が並んでいます。庭園は裏山の景色を取り入れた龍心池(りゅうしんいけ)と、築山(つきやま)のある池泉回遊式(ちせんかいゆうしき)です。
更新日:2018年10月2日
- カテゴリ
-
- 洛東
- 寺院・神社
天台宗の門跡寺院で非常に格式が高く、粟田御所(あわたごしょ)と呼ばれました。天明の大火(てんめいのたいか)の時に天皇が避難 …[続きを読む]
更新日 : 2018年10月2日
-
とよくにじんじゃ豊国神社
豊臣秀吉(とよとみひでよし)をまつる神社で、「ほうこくさん」とも呼ばれています。秀吉は死後、東山の阿弥陀ケ峰の山頂に葬られました。翌年にその山腹に社殿が建てられました。豊臣家が滅亡すると江戸幕府によって取り壊されますが、明治になって政府は、秀吉の功績を称えて現在の場所に豊国神社を新しく建てました。本殿前の唐門は伏見城の門を移したものといわれ、国宝です。柱や扉に鶴や鯉など見事な彫刻が施され、桃山文化の華やかさを実感できます。
更新日:2018年6月28日
- カテゴリ
-
- 洛東
- 寺院・神社
豊臣秀吉(とよとみひでよし)をまつる神社で、「ほうこくさん」とも呼ばれています。秀吉は死後、東山の阿弥陀ケ峰の山頂に葬られ …[続きを読む]
更新日 : 2018年6月28日
-
ようげんいん養源院
豊臣秀吉(とよとみひでよし)の側室淀殿(よどどの)が、父の浅井長政(あさいながまさ)の霊をとむらうために建てた寺院。その後、火災に合い、徳川秀忠(ひでただ)が夫人崇源院(すうげんいん=淀殿の妹)の願いにより、伏見城の一部を移したのが今の本堂。本堂廊下の天井には、伏見城落城のときに廊下で自刃した武士の血のあとが残り、天井に貼って「血天井」といわれています。俵屋宗達(たわらやそうたつ)が描いた杉戸絵や狩野山楽(かのうさんらく)の襖絵(ふすまえ)なども有名なので見てみよう。
更新日:2018年6月21日
- カテゴリ
-
- 洛東
- 寺院・神社
豊臣秀吉(とよとみひでよし)の側室淀殿(よどどの)が、父の浅井長政(あさいながまさ)の霊をとむらうために建てた寺院。その後 …[続きを読む]
更新日 : 2018年6月21日
-
ちしゃくいん智積院
豊臣秀吉(とよとみひでよし)が、3歳で亡くなった長男・鶴松(つるまつ)を弔うために建てたお寺が起こりとされています。何度も災害にあいましたが、1600年に建て直された際、「智積院」と名付けられました。桃山文化を代表する美しい障壁画と庭園で知られています。中でも、長谷川等伯(はせがわとうはく)らによって描かれた「桜図」「楓図」は国宝に指定され、わが国最高の名作のひとつとされています。
更新日:2018年6月21日
- カテゴリ
-
- 洛東
- 寺院・神社
豊臣秀吉(とよとみひでよし)が、3歳で亡くなった長男・鶴松(つるまつ)を弔うために建てたお寺が起こりとされています。何度も …[続きを読む]
更新日 : 2018年6月21日
-
ほうじゅうじ法住寺
後白河法皇の遺骨が納められた法華堂を守ると同時に、身代わり不動尊に対する信仰を集めてきました。明治に後白河天皇陵とお堂が国の管理となり、寺が分離されました。この地は後白河法皇の御所である法住寺殿(どの)があったところ。三十三間堂、新日吉神社、新熊野神社が立ち並ぶ広大なもので、木曾義仲に攻められたこともあります。法皇は、源頼朝から「日本一の大天狗」と皮肉られるような策謀家である半面、芸能を好み、今様を集めて『梁塵秘抄(りょうじんひしょう)』を編集した文化人でした。
更新日:2018年6月21日
- カテゴリ
-
- 洛東
- 寺院・神社
後白河法皇の遺骨が納められた法華堂を守ると同時に、身代わり不動尊に対する信仰を集めてきました。明治に後白河天皇陵とお堂が国 …[続きを読む]
更新日 : 2018年6月21日